
|
率も高い。火災時の防煙区画に十分な注意を払っている筈のアメリカの建物火災でも、人間の避難行動等によって防煙区画が崩れてしまえば、同じことが起こっている。
一一月五日に、中国の唐山市のホテルのケーブルテレビのチャンネルを回していて、偶然NHKのクローズアップ現代を見ることができたが、それはなぜ速く上階に延焼して行ったかを、アクリル板の燃焼実験を使って上手に説明していた。たしかに建築材料の燃焼科学としては納得できるものであったが、建物火災の本質は見逃していた。
建物火災を外から観察していると、どうしても窓から窓へ燃え移っていくように見えてしまうため、建物火災の本質を見逃してしまいがちである。
(六)過去の建物火災事例の教訓
一九八二年二月八日、東京の赤坂にあるホテル。ニュージャパンの九階の客室から火災が発生し、九階、一〇階と燃えて死者三三名、負傷者三四名を出したが、その時の現場のテレビ中継を見ていた専門家の多くが窓窓の延焼だと見ていた。その時、私はそれまでの数多くの現場の体験から、九階の火災の煙が階段室やエレベーターシャフト、設備系のパイプシャフトを伝わって(それを延焼経路と表現させられた)上階に充満し、その煙に下階の炎が燃え移っていったと考え、そのようにテレビで解説したが、しばらくして大新聞の紙上に反論記事が書かれ、窓窓の延焼だと書かれていた。
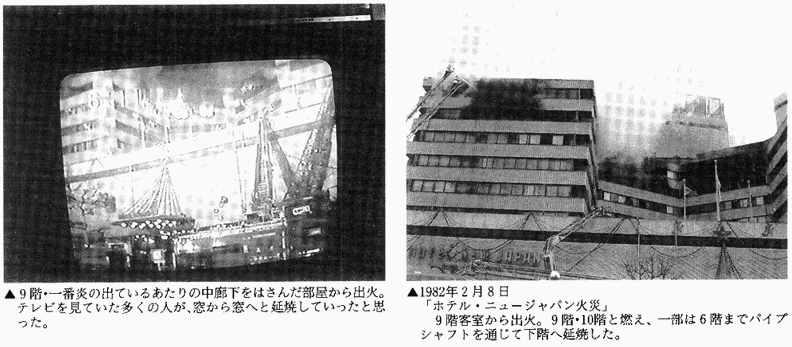
その翌年一九八三年十二月九目に群馬県大間々中学で火災が起こり、鉄筋コンクリート四階建ての耐火建築で、延焼防止のために張り出したベランダを設け、コンクリート製の手摺りであったにもかかわらず、あれよあれよと言う間に、一階で始まった火災が上階に燃え移り、それを見ていた教育長や校長が、耐火建築不信に落ち入ってしまい、半年ぐらい手をつけずに放置してあった。理由は一年前の新間記事が原因で、木造で火災に危険な校舎を、やっと安全な筈の耐火建築の校舎にした筈なのに、あのように簡単に上階に延焼してしまうのであれば、耐火建築物の意味が無いと考え、修理の工事を中止していた。
この大間々中学の火災は、一階の職員室の印刷室あたりから火災が始まり、職員室が真っ赤になり、消防自動車が駆け付けて消火活動を始めたが、すぐに二階に燃え移り二階に放水したが、又三階へ燃え移り、あっと言う間に四階まで燃え上がってしまい、防火区画された半分だけを残して全焼してしまった火災である。この場合も今回と同じように一階の火災現場で生成された熱と圧力を持った不完全燃焼ガスが、タテ穴を通じて上階から下階へと充満していたところへ消防が駆けつけ放水したために窓ガラスが破れて空気が供給され、着火しフラッシュオーバーしながら上階へ燃え上がって行っている。窓ガラスが破れなければ、燃えない筈であった。幸いに二階の一部屋の窓ガラスが、盗難防止のため強化プラスティック製であったため、水で破れずその部屋だけ続け残っていた。そのため私
前ページ 目次へ 次ページ
|

|